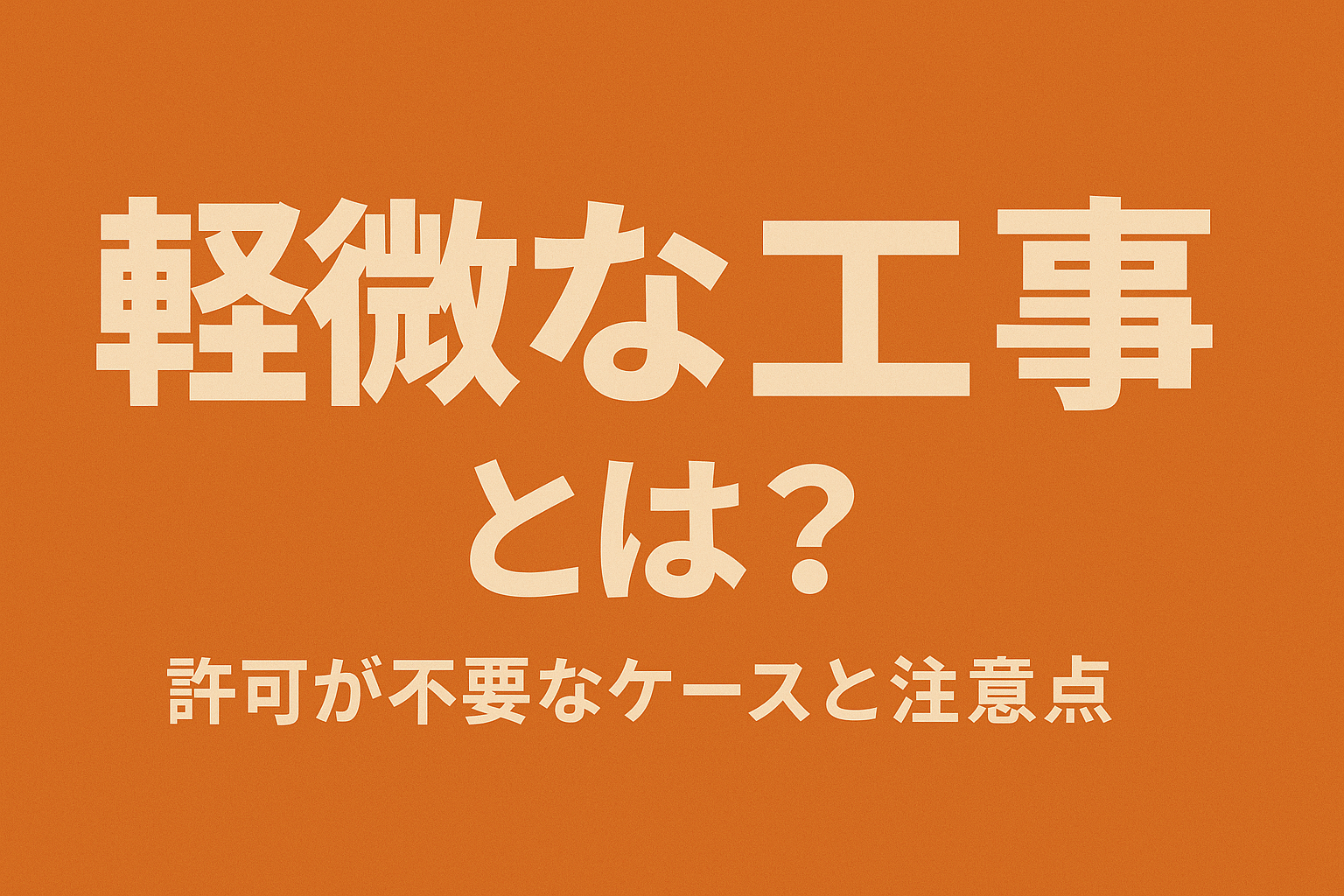建設業を営むうえで、必ずしもすべての工事で「建設業許可」が必要になるわけではありません。実は、建設業法には「 軽微な工事 」という考え方があり、一定の範囲内であれば許可を受けずに工事を請け負うことが可能です。
しかし、「どこまでが軽微にあたるのか?」「材料費や外注費も含むのか?」といった点は、誤解されやすいポイントです。本記事では、建設業許可の境界線となる「軽微な工事」についてわかりやすく解説します。
建設業許可が不要な「 軽微な工事 」の定義
建設業法では、次のような工事は「軽微な工事」として建設業許可が不要とされています。
- 建築一式工事の場合:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
- 建築一式工事以外の工事(とび・土工、内装仕上など29業種):工事1件の請負代金が500万円未満。
つまり、建設業許可がなくてもこれらの範囲であれば工事を請け負うことが可能です。
「請負代金」に含まれるもの
注意が必要なのは、請負代金の範囲です。
単に工事費だけでなく、次のような費用も含まれます。
- 材料費
- 下請業者への外注費
- 人件費
- 諸経費
たとえば「自分は人件費だけだから500万円未満」と考えても、外注先の分や材料費を合算すれば500万円を超える場合があります。この場合、建設業許可が必要となります。
よくある誤解とリスク
- 誤解①:「下請だから許可はいらない」
→ 下請であっても請負金額が基準を超えれば許可が必要です。 - 誤解②:「見積金額が500万円未満なら安心」
→ 実際の契約額が500万円を超えれば、許可なしでの施工は違法となります。 - 誤解③:「工事を分割契約すれば許可不要」
→ 意図的な分割は認められず、全体額で判断されます。
こうした誤解により、無許可営業をしてしまうと、営業停止や罰則といった重大なリスクに直結します。
許可を取得すべきタイミングとは?
軽微な工事で事業を始めても、実績が積み重なれば必ず「500万円を超える工事」を請け負う機会が訪れます。
その段階で許可を持っていないと、元請との取引機会を逃すことにもつながります。
将来的に公共工事や大規模案件を目指す場合は、早めに建設業許可を取得しておくのが得策です。
まとめ
- 「軽微な工事」とは、500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事。
- 材料費や外注費も含めた総額で判断される。
- 誤解による無許可営業は、行政処分や信用失墜のリスクが大きい。
- 将来を見据え、早めに許可取得を検討するのが安全。
岡高志行政書士事務所は、建設業許可申請に強みを持ちます。書類準備や手続きのサポートを通じて、申請者の負担を軽減し、スムーズな許可取得を実現する役割を果たします。適切な書類選定や最新情報への対応が重要であり、建設業許可申請を計画している方には、信頼できる行政書士への相談を強くおすすめします。
参考記事:建設業許可申請の進め方
建設業許可申請は当事務所にお任せください。
ご相談は右下のチャットからも承ります。
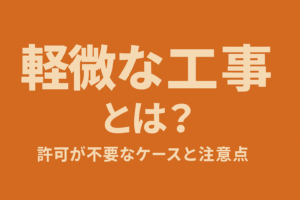
軽微な工事
動画