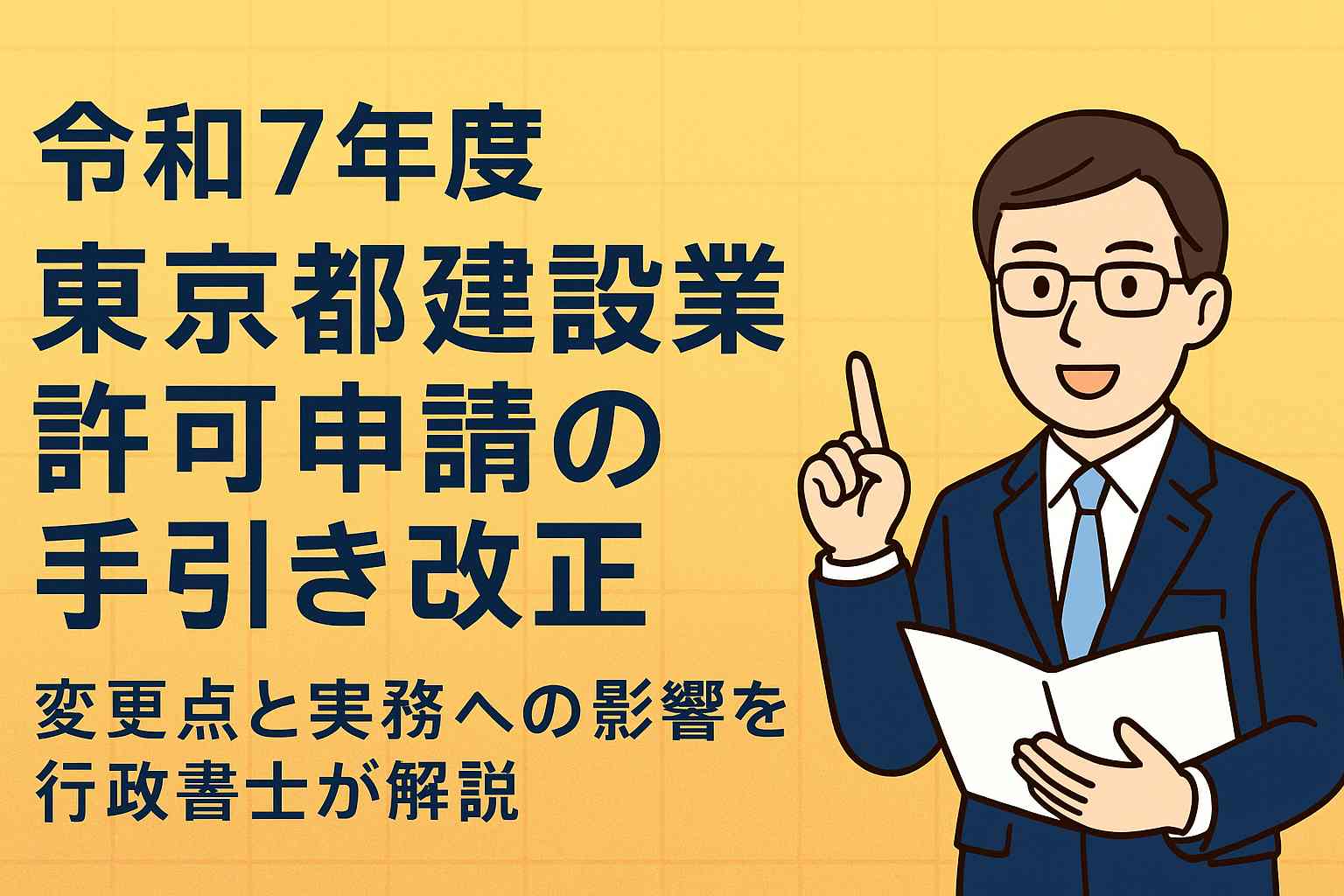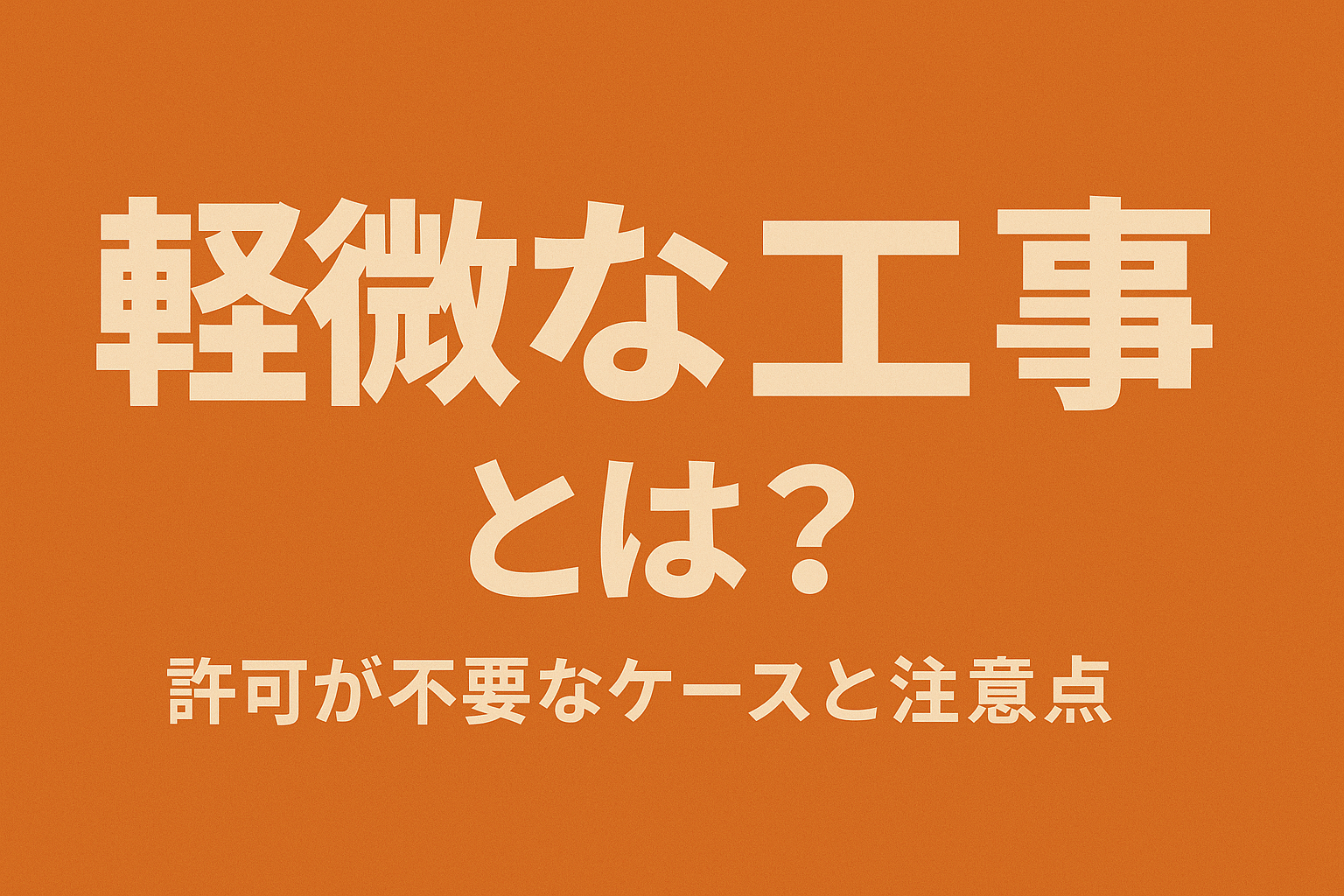東京都では、建設業者が新規に許可を取得したり、既存の許可を更新したりする際に参照すべき公式資料として「 建設業許可申請の手引き 」が毎年度公表されています。令和7年度版の手引きでは、これまでの運用からいくつか重要な変更が行われました。これらの変更は、申請の受付時間や必要な添付資料の取り扱い、さらには特定建設業許可が必要となる下請契約金額の基準など、実務に直結するものばかりです。
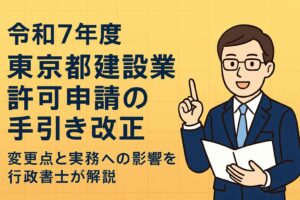
建設業許可申請の手引き
特に、常勤性を確認するための資料が健康保険証からマイナンバーカードや資格確認書へと切り替わる点や、キャッシュレス決済の導入は、現場の手続き方法に大きな影響を与えます。また、登録基幹技能者の範囲が拡大されたことも、企業の技術者配置戦略に関わる重要なポイントといえるでしょう。
本記事では、令和7年度の改正内容を実務家の目線でわかりやすく整理し、それぞれの変更がどのような意味を持ち、どのように準備を進めるべきかを詳しく解説します。これから申請を予定している方や、今後の許可更新に備えたい方にとって、効率的かつ確実に対応するための参考となる情報を提供いたします。
令和7年度 建設業許可申請の手引き 主な変更点
令和7年度版「建設業許可申請の手引き」では、建設業者の実務に直結するいくつかの重要な変更が加えられています。ここではまず全体像を押さえ、詳細は次章以降で解説していきます。
第一に、申請書類の受付時間が見直されました。これまで申請と届出で異なっていた受付時間が統一され、午前9時から午後5時までとなります。ただし、手数料を伴う申請については午前・午後の特定時間帯に来庁する必要があるため、事前確認が欠かせません。
第二に、特定建設業許可が必要となる下請契約金額の基準が引き上げられました。一般建設業で4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)とされていた基準が、5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)へと改正され、一般許可で対応できる工事規模が拡大しました。
第三に、手数料納入方法としてキャッシュレス決済が追加されました。従来の現金納付に加えて、指定ブランドによるキャッシュレス決済が利用でき、利便性が向上しています。
第四に、常勤性を確認するための資料が大きく変わります。これまで広く利用されてきた健康保険証の写しは令和7年12月1日までしか使用できず、その後はマイナンバーカードや資格確認書が必要となります。早めの準備が求められる改正です。
さらに、主任技術者要件を満たす登録基幹技能者に新たに「登録土質改良基幹技能者」「登録都市トンネル基幹技能者」「登録潜函基幹技能者」が追加されました。企業の技術者活用の幅が広がる改正といえるでしょう。
最後に、刑法改正に伴う欠格要件の修正や「専任技術者」という名称の変更など、細かな見直しも行われています。これらは一見小さな変更ですが、書類作成において誤りのないよう注意が必要です。
受付時間の変更と申請実務への影響
令和7年度版の手引きで最初に注目すべきは、申請書類の受付時間の変更です。これまで申請と届出で受付時間が異なり、申請は午後4時まで、届出は午後5時までとされていました。しかし、新年度からは受付時間が統一され、午前9時から午後5時までと明記されました。一見すると利便性が向上したように思えますが、注意しなければならないポイントがあります。
特に重要なのは、手数料の納入が必要な申請の場合です。新規許可や更新許可といった申請では、受付自体は午後5時までですが、手数料の納付は午前9時から11時30分まで、そして午後1時から4時までに限られています。つまり、午後4時以降に窓口に行っても、番号札を発券して手続きを進めることができず、その日の申請は受け付けられません。忙しい建設業者にとっては「夕方にまとめて手続きを」と考えがちですが、今回の改正により時間管理がより重要になります。
また、正午から午後1時までは人員を減らして対応するため、待ち時間が長くなる可能性もあります。効率よく申請を行うためには、午前中の早い時間帯に来庁するか、午後であれば1時直後に訪れるのが理想的です。
この受付時間の変更は、実務において「余裕を持った計画」を求める改正といえます。特に更新申請は期限内に完了させる必要があるため、スケジュール管理を誤ると許可の有効性に直接影響を及ぼしかねません。したがって、申請予定日を早めに決め、必要書類を事前に準備しておくことが重要です。
特定建設業許可が必要となる下請契約金額の引き上げ
令和7年度の改正の中でも、特に建設業者に直接的な影響を与えるのが「特定建設業許可が必要となる下請契約金額の変更」です。これまでの基準では、一般建設業者が請け負う下請契約金額は 4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満) に制限されていました。しかし、今回の改正により、その基準が 5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満) へと引き上げられました。
この改正は、実務において「特定建設業許可が必要となるケースが減少する」という効果を持ちます。つまり、これまで特定許可を取得しなければ対応できなかった工事の一部を、一般許可で対応できるようになるのです。特に中小規模の建設業者にとっては、負担となる特定許可の取得や維持を回避できる可能性が広がり、経営戦略上の選択肢が増えることになります。
一方で、金額の基準が引き上げられたとはいえ、元請として大規模な下請契約を結ぶ場合や、取引先から特定許可の取得を求められる場合は依然としてあります。そのため、自社が取り扱う工事規模や顧客ニーズを正確に把握し、「どの段階で特定許可が必要になるのか」を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
また、この基準変更は、金融機関からの融資判断や元請業者との取引条件に影響を及ぼす可能性もあります。一般許可で請け負える工事規模が拡大したことで、事業拡大のチャンスを掴める一方、リスク管理も一層重要になるでしょう。
参考記事:特定建設業許可 の要件
キャッシュレス決済の導入と申請効率化
令和7年度の手引きでは、申請手数料の納入方法に大きな改善が加えられました。これまで建設業許可の申請や届出に伴う手数料は「現金納付のみ」とされており、窓口での手続きに不便さを感じる事業者も少なくありませんでした。しかし今回から、新たにキャッシュレス決済が利用可能となり、利便性が大きく向上しています。
キャッシュレス決済に対応したことにより、現金を事前に用意する必要がなくなり、窓口でのやり取りがスムーズになります。特に、許可更新や複数案件を同時に申請する場合など、大きな金額の支払いを現金で行うのは煩雑でした。クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス手段が利用できるようになったことで、申請者側の負担は確実に軽減されます。
ただし、利用できるブランドや決済方法には制限があります。東京都の公式ホームページに掲載されている最新の情報を確認し、自社の利用可能な決済手段が対応しているかどうかを事前にチェックすることが重要です。万一、利用予定のキャッシュレス手段が対象外だった場合には、現金を準備しておく必要があるため注意が必要です。
この改正は、行政手続きのデジタル化や効率化の一環として位置づけられます。特に人手不足に悩む建設業者にとっては、時間や労力を削減できる小さくない改善です。さらに、近年は金融機関や事業者間でもキャッシュレス化が進んでおり、その流れに行政手続きが追いついた形といえるでしょう。
結論として、キャッシュレス決済の導入は「利便性の向上」と「業務効率化」の両面で大きなメリットをもたらします。申請予定のある事業者は、この新しい仕組みを積極的に活用し、スムーズな手続きを実現していくことが期待されます。
常勤性確認資料の変更(健康保険証→マイナンバーカード等)
令和7年度の手引き改正の中でも、事業者に最も影響を与えるのが「常勤性を確認するための資料」の変更です。これまで長年にわたり、常勤性を示す資料として広く利用されてきたのは健康保険証の写しでした。しかし、政府の方針による健康保険証の廃止に伴い、建設業許可の申請実務にも大きな転換が訪れています。
具体的には、令和7年12月1日までは従来どおり健康保険証の写しを利用することができますが、令和7年12月2日以降は使用不可となります。その代替資料として、新たに以下のいずれかを提出する必要があります。
-
マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面
-
資格確認書(※「資格情報のお知らせ」とは異なる別書類)
ここで注意すべきは、証明期間が令和7年12月1日以前であっても、申請・届出日が12月2日以降であれば健康保険証の写しは不可とされる点です。つまり、日付をまたぐことで「使えると思っていた書類が急に使えなくなる」というリスクがあるため、早めの準備が欠かせません。
また、マイナンバーカードを利用する場合、従業員が必ずしもカードを所持しているとは限らないため、社内での事前確認が必須です。資格確認書を選ぶ場合も、発行手続きに時間がかかる可能性があるため、直前対応では間に合わないケースが想定されます。
この改正は、単なる書類の差し替えにとどまらず、申請準備の進め方そのものに影響します。特に年末以降の申請を予定している企業は、早急に対応方針を決めておくことが重要です。行政書士としても、申請スケジュールを立てる際にはこの変更点を必ず考慮するようアドバイスしています。
登録基幹技能者の追加と主任技術者要件
令和7年度版の手引きでは、主任技術者の要件を満たす登録基幹技能者に新たな区分が追加されました。これまでにも解体、鉄筋、配管、電気工事など多岐にわたる基幹技能者が主任技術者として認められてきましたが、今回新たに次の3種類が加わりました。
-
登録土質改良基幹技能者
-
登録都市トンネル基幹技能者
-
登録潜函基幹技能者
これらの技能者は、建設業法第26条第1項に定められた主任技術者の要件を満たすものとされ、特に土木や地下工事の分野において、主任技術者としての配置可能範囲が広がることになります。これにより、専門性の高い技術を有する人材を戦略的に活用できる企業にとっては、競争力強化の大きなチャンスとなるでしょう。
ただし、主任技術者として認められるのは一般建設業許可に限られる点に注意が必要です。特定建設業許可の主任技術者要件を満たすわけではないため、企業の事業規模や請け負う工事の内容に応じて、適切な許可区分との整合性を確認することが欠かせません。
また、基幹技能者の認定を受けるためには、所定の講習修了や実務経験の証明が必要です。したがって、企業側は「どの技能者が自社にとって主任技術者として活用できるのか」を早期に洗い出し、将来の人材配置計画に反映していくことが求められます。特に専門工事業者や下請比率の高い事業者は、この変更をうまく活用することで、より幅広い工事案件に対応できる体制を整えることが可能です。
その他の改正と実務対応
令和7年度版の手引きでは、大きな制度変更以外にも、申請実務に影響を及ぼすいくつかの修正が加えられています。これらは一見すると小さな変更に見えますが、実務の現場では見落としがちなポイントですので注意が必要です。
まず、刑法改正に伴う欠格要件の修正です。建設業許可には欠格事由が定められており、一定の刑罰歴や違反歴がある場合、許可を取得・維持できません。今回の手引きでは、刑法の改正を反映する形で欠格要件の記述が見直されています。これにより、過去の法令表記を前提に書類を作成すると不整合が生じる可能性がありますので、最新の記載に基づいて書類を整えることが重要です。
次に、「専任技術者」という呼称が「営業所技術者等」へ修正されました。名称の変更は一見些細に見えますが、正式な書類作成においては誤記があると差し戻しの対象となりかねません。過去のひな型を流用する場合は特に注意が必要です。
さらに、手引き全体を通じて、文言や体裁の細かな調整が行われています。これにより、同じ内容であっても記載方法や表現が若干異なる箇所があり、過去の知識や経験に頼りすぎると見落としが発生する可能性があります。
行政手続きにおいては、些細な修正であっても「形式的に正確であること」が求められます。そのため、実務担当者は最新版の手引きを必ず参照し、改正点を正確に把握することが求められます。特に更新申請や新規申請を控える企業は、古い情報を基に作成した書類をそのまま提出しないよう徹底することが肝要です。
行政書士からのアドバイス
今回の令和7年度版手引きの改正は、見逃すと申請不備につながりやすい内容が多く含まれています。ここでは、実務を数多く経験してきた行政書士の立場から、特に注意すべき点と実務的な対応策を整理します。
まず、申請スケジュールの管理が何より重要です。受付時間は延長されたように見えても、手数料納入が可能な時間帯は制限されています。午後遅い時間に来庁しても受付できないケースがあるため、早めの来庁を基本とし、特に更新申請では期限直前に駆け込み提出することがないように計画的に準備しましょう。
次に、常勤性を示す資料の変更は大きな落とし穴です。健康保険証の利用が終了する令和7年12月以降は、マイナンバーカードや資格確認書が必須となります。従業員がカードを未所持の場合や資格確認書の発行に時間がかかる場合、申請が遅れる可能性があります。社内で早めに所持状況を確認し、必要に応じて準備を進めることが肝要です。
さらに、特定建設業許可の判断基準の変更や基幹技能者の追加といった制度面の見直しは、自社の事業計画や人材戦略に直結します。一般許可で請け負える工事規模が拡大したことはプラスですが、取引先から特定許可を求められるケースは残るため、契約先の要件も含めて総合的に判断する必要があります。
最後に、書類の名称変更や体裁の修正も軽視できません。過去の雛形をそのまま利用することで誤記が発生し、差し戻しにつながることは少なくありません。常に最新版の手引きを参照し、細部まで確認する姿勢が大切です。
申請は一度の不備で大きく遅れることがあります。専門家に相談することでリスクを減らし、効率的に許可取得を進められる点は大きなメリットといえるでしょう。
行政書士としての立場から強調したいのは、「最新版の手引きを正確に参照し、不備のない書類を整えること」です。わずかな誤記や旧情報のままの申請が差し戻しや遅延を招くことは珍しくありません。専門家に相談することで、無駄な時間やコストを省き、確実な許可取得を実現することができます。
建設業許可の取得・更新を予定している方は、ぜひ早めの対応を心掛け、必要であれば行政書士にご相談ください。チャットボットからもお気軽にお問い合わせいただけます。